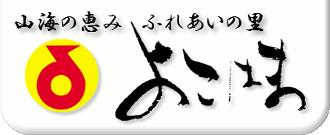児童扶養手当
この手当は、父母の離婚、父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されるものです。なお、児童が18歳に達した年度末まで手当の支給の対象となります。児童が政令で定める障害を有するときは、児童が20歳に達するまで支給されます。
★支給対象者
次のいずれかの状態にある児童(18歳の誕生日を迎えたあとの3月末までの者、心身に中度以上の障害を有する場合は20歳未満の者)を監護する母、又は監護し、かつ生計を同じくする父、若しくは父母に代わって養育している者に手当が支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害状態にある児童
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
【障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の児童扶養手当が変わります。】
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
2.支給制限に関する所得の算定が変わります
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※2)が含まれます。
(※2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります [525KB pdfファイル]![]()
★支給の対象外
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません
- 受給資格者の住所が日本国内にないとき
- 児童の住所が日本国内にないとき
- 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く)
- 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき(父又は母の配偶者の障害が受給理由の場合を除く)
★所得制限額
| 扶養親族等の数 | 受給者本人 |
孤児等の養育者・ 配偶者・扶養義務者 |
|
|---|---|---|---|
|
全部支給 |
一部支給 | ||
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
|
4人 |
2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
また、所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族、特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額が所得制限限度額となります。
- 本人の場合 (1)同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき10万円 (2)特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
- 孤児等の養育者 配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
★手当額
〈令和7年4月からの児扶法に基づく手当額〉※所得に応じて決定されます。
| 児童扶養手当額 |
全部支給(月額) |
一部支給(月額) |
| 第1子(本体額) |
46,690円 |
46,680~11,010円 |
| 第2子加算額 |
11,030円 |
11,020~ 5,520円 |
平成29年4月より、子どもが2人以上の場合の加算額にも物価スライド制が導入されました。 物価スライド制とは、 物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて、支給する額を変える仕組みをいいます。
・3、4月までの分は、5月11日に支給されます。
・5、6月までの分は、7月11日に支給されます。
・7、8月までの分は、9月11日に支給されます。
・9、10月までの分は、11月11日に支給されます。
・11、12月分までの分は、1月11日に支給されます。
・1、2月分までの分は、3月11日に支給されます。
※11日が土曜、日曜、祭日の場合はその前の日に支給されます。